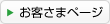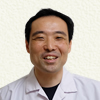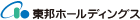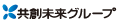健康アイテムの選び方
過去の健康アイテムの選び方はこちら
【第2回】近ごろよく耳にする『糖質』とは?
「糖質」ってそもそも何?どうしたらいいの?ちょっと気になりますよね。
今回は「糖質と健康」についての耳よりなお話です
糖質は、大切なエネルギー源
糖質とは、炭水化物から食物繊維を除いたもののこと。米、小麦などの穀類、ジャガイモ、サトイモなどのいも類に豊富に含まれている栄養素です(表参照)。
たとえば、30~40代女性の推定エネルギー必要量(※1)は1 日におよそ2000kcalで、炭水化物の摂取基準は、その50~65%(エネルギー比率)とされています。50%とすると炭水化物は約250gとなります。
糖質は、毎日しっかりと必要な量を摂らなければいけません(※2)。
※1 30~49歳女性 身体活動レベルⅡの場合 「日本人の食事摂取基準」2015年版(厚生労働省)
※2 たんぱく質、糖質は1gあたり4kcal、脂質は1gあたり9kcal
糖質の摂りすぎが生活習慣病と肥満のもとに
問題なのは、糖質を多く摂りすぎることです。 糖質はエネルギー源として、体内でどんどん消費されていきますが、消費量以上の糖質を摂れば、当然、あまります。あまった糖質は脂肪として蓄積されるので多く蓄積されていくと肥満につながります。
また、糖質の摂りすぎなどで食後の血糖値が急上昇したり、上がりすぎて高い状態が続くと糖尿病や動脈硬化などを引き起こし、様々な病気につながるおそれがあります。
最近、糖質制限という言葉をよく耳にします。糖尿病患者、メタボリックシンドローム予防やダイエット志向者用の食事療法ですが、食後の血糖値の上昇をなだらかにすることを目的としたものです。ダイエット目的などでは、糖質の摂取量を1食40g程度、1日に約130gにする、といわれていますね。
□ カツ丼、親子丼、牛丼など丼ものやカレーライスなどのご飯ものが大好き
□ うどんやそば、ラーメンなどのめん類をよく食べる
□ 「ラーメン・チャーハンセット」や「そば・かやくごはんセット」が好き
□ パンにジャムをたくさんつけて食べるのが好き
□ 毎日おやつにケーキ、チョコレートなど甘いものを食べる
□ 出来あいのお弁当をよく食べる
□ 甘い飲料をよく飲む
□ 朝食を抜いてしまうことが多い
□ 早食いである
丼ものやめん類、一品ものなどは、糖質量が大幅アップ
では、糖質を摂りすぎないために、気をつけるべきことは?
ポイントは主食の見直しです。ごはんお茶碗1杯(150g)で糖質量は約55gです。主食、主菜、副菜をバランスよく食べることが重要ですが、忙しい現代人の食生活は、炭水化物にかたよりがちです。
簡単にお腹を満たそうとすると、ラーメンや丼もの、カレーライスなどの「めん類」や「一品もの」ですませてしまうことも多いのではないでしょうか。でも、これらのメニューには要注意。丼ものには、ごはんが1食で約250~300g、糖質量は約92g~110gにもなります。
では、いっそのこと、一日2食でもだいじょうぶ?
NGです。食生活の基本は「1日3食」を心がけることです。2食だと空腹時間が長くなり、その後の食後の血糖値が上がりやすくなってしまいます。
食べる順番や糖質の多い野菜にも気配りを
食べる順番にもコツがあります。はじめにサラダ、次に主菜の肉・魚、副菜の糖質以外のものを食べ、最後に糖質を摂る。糖質の吸収が遅くなり、食後の血糖値の上昇をおだやかにすることができます。また、おやつなどに、消化吸収に時間のかかるナッツ類を食べるのもオススメです。
また、野菜はビタミンやミネラル、食物繊維が豊富なので積極的に摂取したい食材ですが、糖質の多い野菜もあります。たとえばカボチャは糖質が多いので、カボチャの煮物やサラダなどは量に気をつけていただきたいものの一つです。昼食で「ラーメン+チャーハン」「そば+かやくごはん」の組み合わせがよくありますが、これは「糖質+糖質」の組み合わせなので、かなり糖質の多い食事になってしまいます。
また、加工食品やコンビニのお弁当を食べるときは、栄養成分の表示を確認することを心がけてみてくださいね。
主食の見直しや食べる順番、加工食品の栄養成分を意識するだけで、無理のない糖質コントロールができるようになります。さっそく今日から、始めてみませんか?